記事を検索する
「あの本がつなぐフェミニズム」第10回:『私は女』(大橋由香子)
2025/10/14

パソコンもネットもスマホもないころ、女たちは刺激的な考えや情報を雑誌や本から得ていた。今あらためて「あの本」のページを開くと、何があらわれるのだろうか。連載第10回は、およそ40年前、自身も障害をもつ編者ふたりが、日本各地の女性障害者を訪ね、恋愛やセックス、結婚、月経、子宮摘出など当時「タブー」とされていた話を聞き取った「あの本」について。40年前から今にいたる、障害者運動、優生保護法との戦いなど振り返りながら、この本に登場する「声」が問いかけるものを考えます。
(バナー写真:フィリピンの女性たちとの屋外学習@マニラ1987年。背景写真は1982年優生保護法改悪阻止集会@渋谷山手教会、左の旗は1984年女と健康国際会議@オランダ/すべて提供:大橋由香子)
2025年、長く暑い夏の9月3日から22日まで、東京・赤羽の青猫書房で「花咲か北さんとファンキー西さん」と題した展覧会が開かれた。(ポスター参照)

子どもの本屋さんの奥のギャラリーには、北三郎さんが「お花紙」で作った梅や菊や紫陽花の造花が飾られた。西スミ子さんの昔と今の写真とともに、西さんが施設を出て自立生活をするまでを聞き書きした原稿用紙や介助者募集チラシがラミネート加工されて読めるようにテーブルに置かれていた。
北さんと西さんは、優生保護法による強制不妊化の不当性を訴えて国賠訴訟を東京地裁に起こし、2024年の最高裁判決で勝訴した。「原告」という肩書きだけではない、二人の姿を知ってもらいたいと企画された。
西スミ子さんが千葉の施設から脱出して、道ゆく人たちに声をかけ、車椅子を押してもらって大阪にたどりついた経験も原稿用紙に記されていた。ロックでファンキーな彼女の人生を知ると、これまで出会ったいろんな女(ひと)を思い出す。私の場合、1982年の優生保護法改悪阻止連絡会に関わる前後から、障害者運動に関わる女たちと知り合うようになり、1995年北京女性会議のNGOフォーラムでは、大勢で参加した車椅子の女たちと「優生保護法って何?」というワークショップをした。
彼女たちが語っていたことは、1984年に刊行された『私は女』(長征社)に登場する重度女性障害者の経験とも重なっていた(本では関西弁の人が多いせいか雰囲気は違うけれど)。

『私は女』の編者は二人。岸田美智子さんの「子宮とのつきあい」という文章から本書の企画が生まれ、芝居を始めていた金満里さんと一緒に、関西や九州を中心に女性障害者を訪ねて話をきいた。家族との関係、就学免除で小学校に行けなかったこと、施設での不自由さ、恋愛やセックスや結婚、月経の苦労、子宮摘出……タブーとされたことが語られていく。
約40年前に49歳だった大阪に住む脳性まひの森野和子さんは、こう話す。
「そのじぶん[時分]は『子宮」ということば自体知らん、ほんでまた、私らの時代やから『これは不浄のもの、女の汚(けが)れやから、弟たちに見られたらあかん』と、それだけをきつく注意されたん。/毎月あるもんとも知らん、自分が不順とも知らん、ものすごうおなかが痛なって、はじまったら一週間、ね、何のためにあるのかもわからんで、そのあいだずっと、二時間もしたら身体じゅうが汚れる。それがうとましくてうとましくて、どないかしてほしいと思ってたところに、生理をなくす手術があると聞いたから、自分からすすんでしてもらった。」
母親が病院に何回か行き、準備ができていた。森野さん本人が診察室に入ると、
「まずお医者さんのいったことは『これは法律で禁じられている手術である以上、ぼくにも責任ないとはいえんけど、あなたがたも、どこにも口外せんよう約束できますか』ということで、私も『約束します』とはっきりいうた。」(『私は女』224p [ ]は引用者の補足)
優生保護法では、不妊手術を「生殖腺を除去することなしに」生殖能力をなくすと定めているので、理由なく子宮や卵巣を取ってしまう(摘出)のは法律違反だと医師も認識していたのだろう。でも、家族や施設の職員に迷惑をかけないための子宮摘出は、公然の事実のように女性障害者になされていた。ちなみに、優生保護法の定めた術式(卵管を縛るか切る)では、妊娠はしなくなるが月経はなくならない。
「女」として恋愛対象に見られない、セックスも結婚も出産も子育ても無理と決めつけられ、あきらめることを強いられる中で、サバイブしてきた怒りとパワーが伝わってくる。本には、親と同居の人も、ひとり暮らしの人も、結婚して子育てしてる人も登場する。夫に障害がある人もない人も、いい関係が続く人もいれば、離婚した人もいる。家や施設から出るためには介助者を集めなければならず、障害者サークルや運動、宗教も絡んでくる。そこでの性暴力も書かれている。
当時25歳、脳性まひ、兵庫の女性は……
「結婚したら男は変わるというけど、あんなに変わると思わなかったよ。結婚するまえは、外ヅラやってん。内ヅラがわかったら、ほんまにこわいで。それ、見抜けなかったもんな。(略)
だいたい私は、子どもはあんまり欲しいことなかった。せっかく家を出られたとこやもん、もうちょっと自分の好きなことをやりたいと思った。それと、出産のときは体力をつかうから、子どもをうんで、よけい重度になったひとも、何人か知ってたしな。(略)
避妊いうても膣外射精だけやったもん、結婚して一カ月もたたんうちに妊娠してしまった。私は、『堕ろしたい、堕ろしたい』の一点ばりやったけど、彼は『あのひとも、あのひとも、あのひとも、うんでるやんか』と、重度のひとの名まえをあげて、中絶はぜったいあかんて、がんばってな。単なる重度女性障害者のダンナというよりも、子どもをうんだ女性障害者のダンナになれば、大きな顔ができるもんな。ふだんは、何かあったらすぐ、私の実家のお母ちゃんに子どもを預けるくせに、集会のときだけは、私に子どもを抱かせて出るからな。私が子どもを抱けるのはそのときだけ。」(『私は女』160-161p)
このインタビューの一週間後に、離婚したという報告も追記されている。
本当に、人生いろいろだけれど、女であることと、障害者であることが折り重なってくる重み。つぶされまいと生きる彼女たちの声は、まさに障害者解放と女性解放(フェミニズム)との不協和音でもあり、私のような障害のない女への糾弾でもあった(注)。
金満里さんは、こう書いている。
「……障害者だからかえって自由に生きれる側面があると思うのよ。地域からも、家族からも、何からも期待されず、いうたら疎外されてるわけでしょう。だったらさ、好き勝手せざるをえないやん。完全に障害者というところで居直りきったらさ、もっともっと、いろんなことができると思うんだけどな。」(『私は女』255 p)
ぜひ多くの人に読んでほしい(1995年に新版が出たそうだが品切れ。私が読んで引用しているのは84年版)。
*
『私は女』に出会った後の自分を振り返ってみる。
優生保護法から優生条項が削除された1996年のあと出会ったのが、広島の佐々木千津子さん。施設に入るには月経をなくさなくてはいけない、「痛くもかゆくもない」とだまされて、レントゲン照射を受けた。ところが副作用はひどく、優生保護法(にすら違反する)被害をずっと訴えてきた。宮城県の飯塚淳子さん(仮名)と一緒に、1990年代後半から国会や厚生省にロビイングしてきた。
映像ビデオ「忘れてほしゅうない」(優生思想を問うネットワーク)は、「ひん曲がった根性で、裏向いて生きてやる」という千津子さんのセリフから始まる。スーパーで缶ビールを買い、髪をピンクに染める日常が映し出されていた。国賠訴訟が起きる前に亡くなってしまい、本当に悔しい。追悼文集『ほぉじゃのぉて』(2014年、追悼文集編集委員会:てごーす、てれれ、ゆじょんと)の中の写真、はにかんだ笑顔がなつかしい。
そして、車椅子ユーザー青海恵子さんと私との往復書簡『記憶のキャッチボール-子育て・介助・仕事をめぐって』(インパクト出版会)を出したのは2008年。コスタリカで開かれた第5回女と健康国際会議に一緒に参加し、同じ区に住んでいて、フェミ友には子どものいない人が多いので、子育ての愚痴を言い合っていた。その最中の往復書簡だった。最近はマゴ話も出てくるようになり、涼しくなったから、また会いに行こう。

*
『私は女』から40年。さまざまな運動の成果で、国も障害者差別をなくすための施策を(不十分ながらも)進め、学問の世界でも「障害学」が市民権を得て研究が蓄積している。その中で、性差別やジェンダーに注目した本や映画表現も生まれている。
2023年に刊行された『障害があり女性であることー生活史からみる生きづらさ』(土屋葉 編、現代書館)には9人の研究者などが寄稿し、障害者への聞き取り調査をもとに、複合差別、交差性(インターセクショナリティ)を論じている。瀬山紀子「第10章 語られ、問い返され、重ねられてきた経験」では、1980年代の月経・子宮摘出問題をめぐる対話を印刷物から記録し、『私は女』の鈴木利子さんの言葉が引用されている。また、本ウェブ連載3回目に紹介した『女たちのリズム』での堤愛子さんの問題提起も紹介されている。
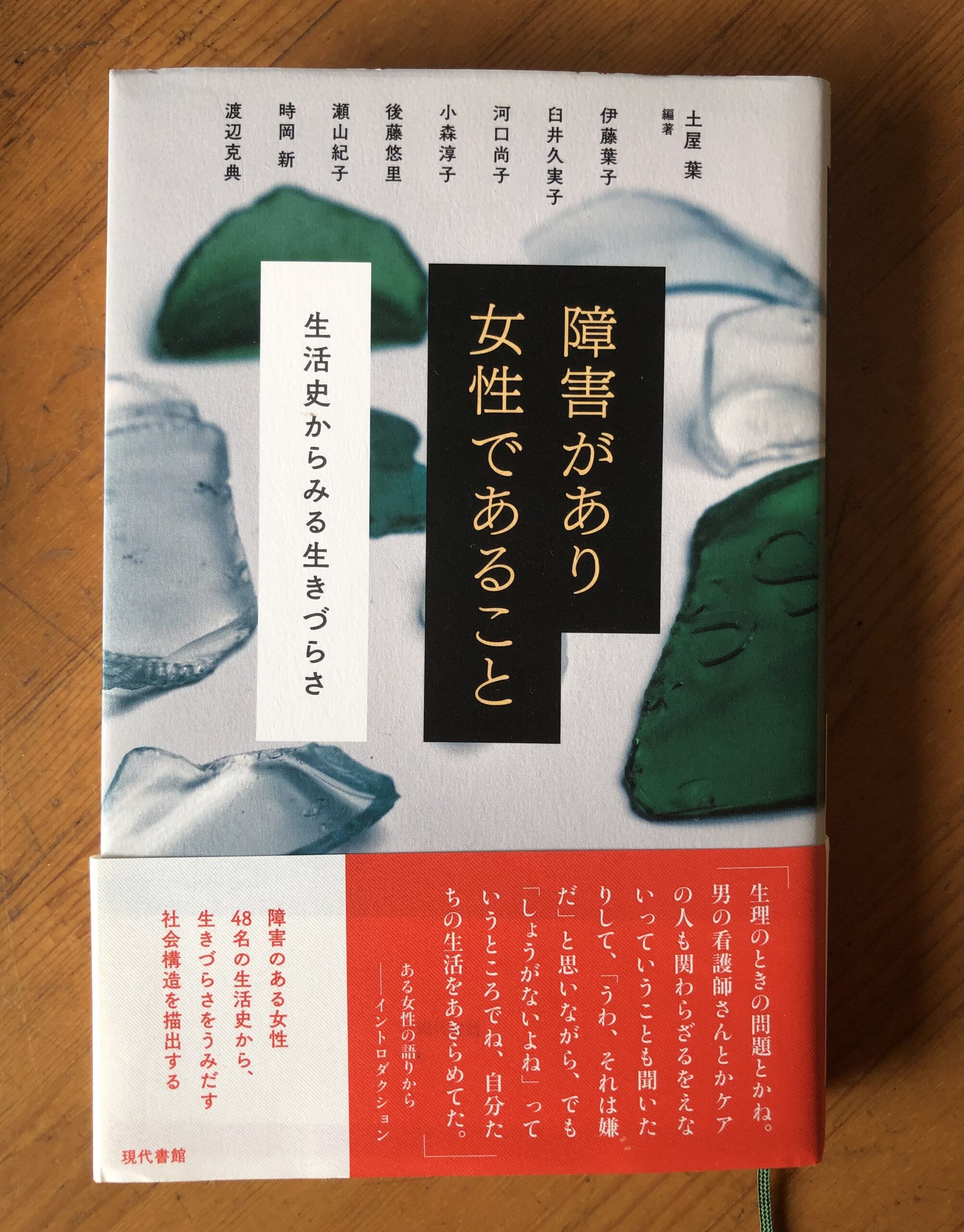
経験を文字にすること、歳月とともに変わる・変わらないことを記録すること、そこから見えてくるものが、たくさんある。その豊かさを感じる一方、相模原事件も経験したこの国で、劇団態変を主宰してきた金満里さんの40年前の言葉を、今こそ噛みしめなければいけない。
「(略)たまたま私らは、正真正銘の障害者やから、はみ出たまんまで居直って生きていくことで、対立というよりも、健全者が潜在的にもっている『はみ出したい、はみ出せない』という気分をくすぐるだけでさ、つながっていけるという自信があるからやっていけるようなもんでね。/でもそのつながりかたが『あいつらがあんなに好き勝手に生きとんのに、なんで自分らががんばらなあかんねん、バカバカしい、やめた』となれば正解なんだけども、逆に『自分らがこんなにがまんしとんのに、あいつらにあんなに好きに生きられたらたまらん、やっつけてまえ』となる可能性もあるわけで、私なんか街を歩いてたりして、ときどき殺気を感じることがあんのね。」(『私は女』259p)
脱原発運動や優生保護法国賠訴訟で、東京で何回も会った古井正代さんも2025年6月に亡くなり、「辛気くさい葬儀なんかいらん」と「正代祭り」になったという。
みんながずっと謝罪や補償を求めてきた優生保護法について、2025年10月1日、第1回検証委員会が開かれた。やっと!
性差別と優生思想=障害者差別をえぐり出してきた彼女たちの肉声に、しっかり応答したい。
(注)こう書くのには、もちろん、ためらいも感じる。異性との恋愛や結婚制度が今以上に強固な時代に、そこから排除された障害をもつ女たちの「カレシ」への憧れ、障害がない女に押し付けられる「女らしさ」すら奪わる現実など思いながらも、表紙イラストにモヤモヤしたのを覚えている。1995年北京女性会議に参加し、報告集『ありのままの女(わたし)が好き!―第4回世界女性会議 NGOフォーラム参加報告集』(DPI女性障害者ネットワーク、女のからだから‘82優生保護法改悪阻止連絡会、フィンレージの会、若い声、コウ・カウンセリングの会、1995年刊、からいす企画)の編集作業をしながら、そのモヤモヤが少し晴れた気がする。
*おススメ新刊書
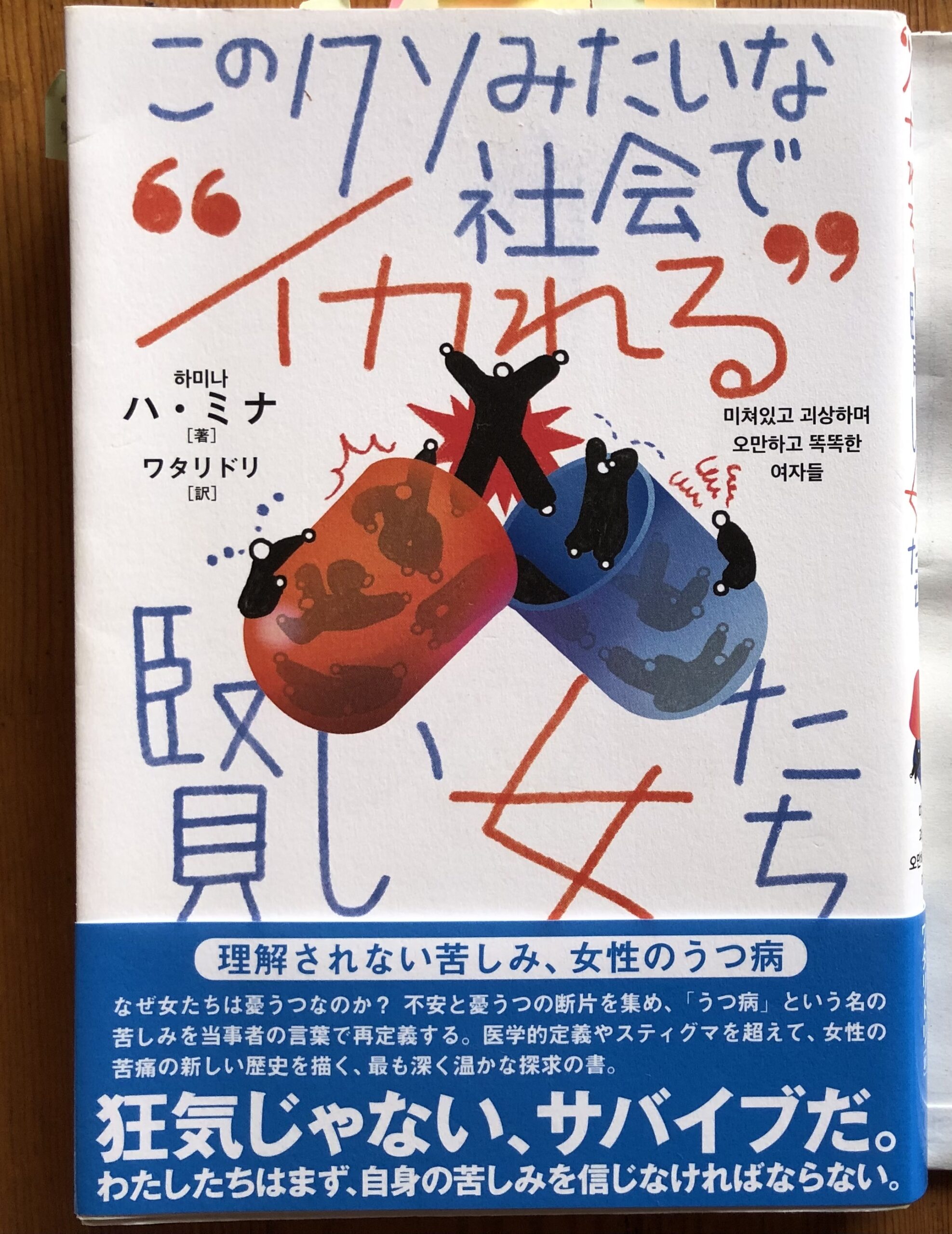
『このクソみたいな社会で”イカれる”賢い女たち 理解されない苦しみ、女性のうつ病』
(ハ・ミナ著、ワタリドリ訳、明石書店)
躁うつ病の当事者である著者が、自分と同じ20代から30代のうつ病女性33人にインタビューし分析した本。親からの暴力、貧困、学校での序列、恋人からのデートDV、職場での日常的なセクハラ、医療における性差別など、社会的な要因が浮き彫りになる。期待される患者像を拒否し、「イカ」れている自分を受けいれ、時にイカ(怒)り、ケアや回復の道すじを共同で模索する。精神障害における性差別も万国共通かも。
*新しい本が2冊でました。
『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』
AERA「この人のこの本」に著者インタビューが掲載されました。

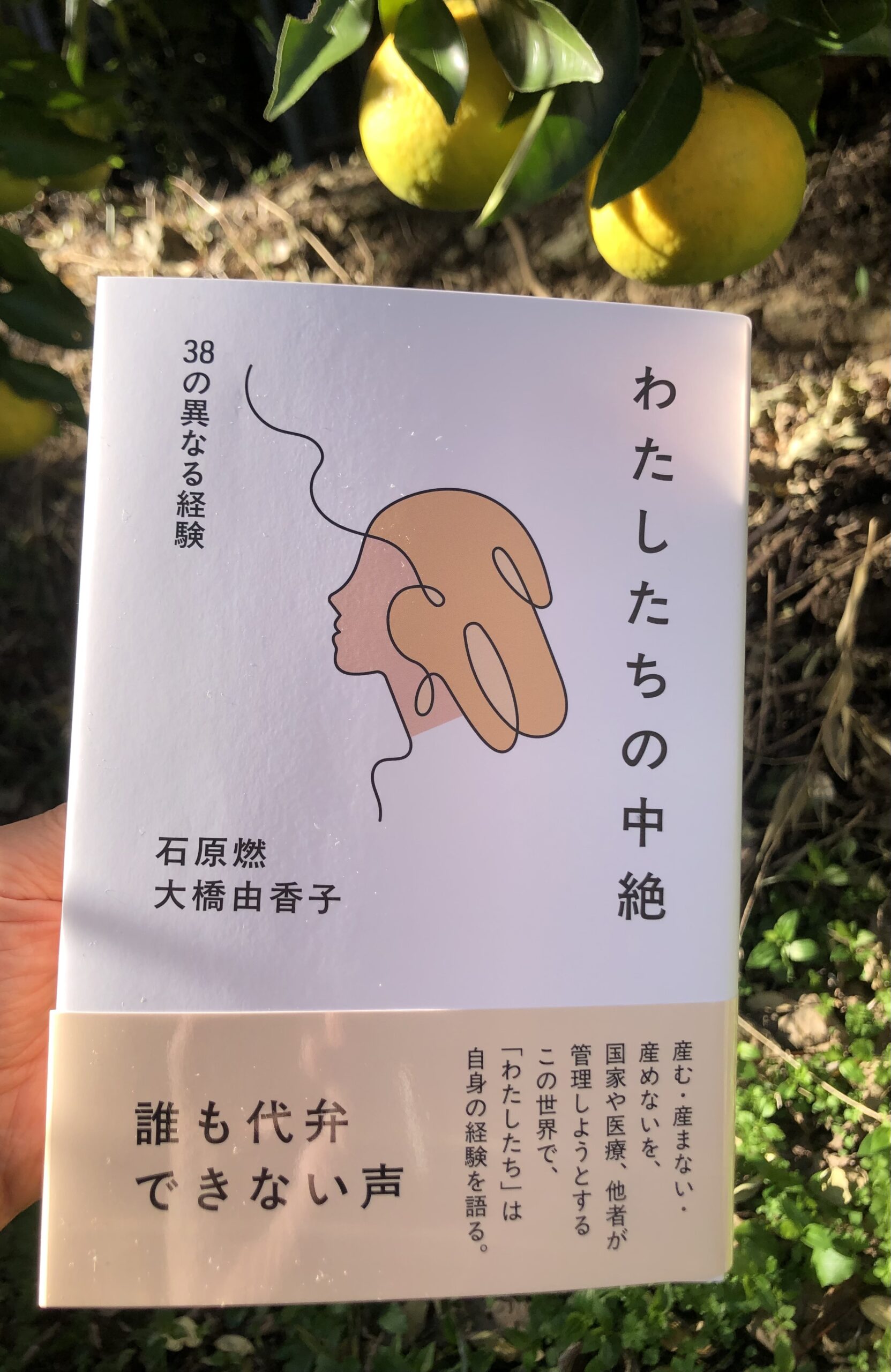
大橋由香子(おおはし・ゆかこ)
フリーライター・編集者、非常勤講師。著書に『満心愛の人―フィリピン引き揚げ孤児と育ての親』(インパクト出版会)、『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』(エトセトラブックス)、共編著『福島原発事故と女たち』(梨の木舎)、『わたしたちの中絶』(明石書店)ほか。光文社古典新訳文庫サイトで「字幕マジックの女たち:映像×多言語×翻訳」連載中。白水社のPR誌「白水社の本棚」2025夏号に「小尾芙佐さんのこと」を寄稿。小尾さんについてより詳しいことは、『翻訳する女たち』をぜひお読みください。
大橋由香子「あの本がつなぐフェミニズム」
- feminista
- nomore女人禁制
- あの本がつなぐフェミニズム
- ヴァージニア・ウルフ
- エトセトラ
- エトセトラ VOL.6
- カルメン・マリア・マチャド
- カン・ファギル
- すんみ
- フェミニスト出版社
- フェミ登山部
- みんなでパブコメ
- よこのなな
- ラテンアメリカ
- 伊藤春奈(花束書房)
- 堀越英美
- 大橋由香子
- 女人禁制
- 小山さんノート
- 小山内園子
- 小林美香
- 小澤身和子
- 山内マリコ
- 山姥
- 山田亜紀子
- 岩間香純
- 新水社
- 松田青子
- 枇谷玲子
- 柚木麻子
- 牧野雅子
- 王谷晶
- 田嶋陽子
- 田房永子
- 石川優実
- 福岡南央子
- 緊急避妊薬を薬局で
- 翻訳する女たち
- 翻訳者たちのフェミニスト日記
- 部落フェミニズム
- 鈴木みのり
- 長田杏奈
- 高柳聡子







