記事を検索する
「翻訳者たちのフェミニスト日記」NO.11:母を葬る旅――ロシアのフェミニスト詩人オクサーナ・ヴァシャキナの長編『傷』(高柳聡子)
2021/11/14
海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの第11回は、ロシア語翻訳の高柳聡子さんによる、ロシア文学を変えるであろうひとりのフェミニスト詩人・作家について。
ロシア文学はある転換点を迎えた、そんな気がしている。ロシアに新しい文学が登場したと。彼女の言葉は、こんな文学を待っていた世界中の読者に届きはじめている。
オクサーナ・ヴァシャキナは1989年にシベリアのウスチ・イリムスクという小さな町で生まれた。水力発電所と材木工場のために建設された人口10万人ほどの町は、ソ連崩壊後の経済危機のさなかに育ったオクサーナにとって子ども時代の貧困の記憶の舞台だ。
長距離トラックの運転手だった父はエイズで、材木工場勤めだった母は癌で亡くなった。現在、ロシアのフェミニスト詩人の中でももっとも有名なヴァシャキナが今年発表した長編小説『傷』は、過酷な彼女の生をありのままに記述し、散文と詩が混在する多層的なテクストだ。
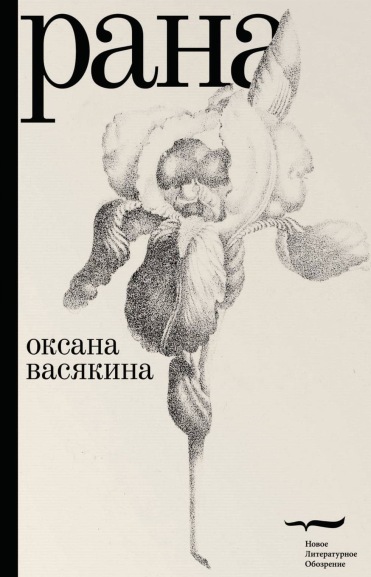
オクサーナ・ヴァシャキナ『傷』
ここには、驚くほど率直にまっすぐに自身のセクシュアリティ、同性愛者であることへの罪の意識、恐怖、不安、そして痛みとともに母への愛を語るフェミニスト詩人の誠実な姿があり、幾度も立ちどまり、ページから顔を上げ、胸を鎮めながら読み進めなければならない。そうして、私人としてのオクサーナと作品の「私」とにどんどん惹かれていく(たぶん彼女は私生活と創作を区別する気がない)。
物語の軸となっているのは、今はモスクワに暮らす「私」がホスピスで亡くなった母の遺骨を引き取り、故郷シベリアの祖母の隣に埋葬するために10年ぶりに帰省する旅の記録だ。けれどもこれは一筋縄ではいかない。広大なロシアの地を東へ、母の遺体を引き取り火葬し、骨壺を抱えて一旦モスクワへ(仕事がたまっていた)、遺骨と二カ月暮らした後に再び東へと向かう――列車やバスや飛行機を乗り継ぐ長い旅のなかで彼女が想起する過去の記憶、フェミニズムをめぐる思索、頭に浮かんだ他人の詩、自分の詩、そしていちばん大切な母との思い出……が時系列もばらばらに思いつくままに語られながら、オクサーナとその母、祖母の人生を繋ぐ年代記のように、シベリアに生きた名もなき人たちの生が浮かび上がっていく。
その中でしばしば語られるのが母への「ふるえるほどの愛」だ。14歳の時に詩を書き始めたのは、母に見てほしかったから。詩のノートを母の目につく場所に置き、ほめてもらうことを期待するオクサーナ。けれども「母は男性を愛する能力はあったけれど、私を愛する能力はなかった」。母の死後、オクサーナは詩が書けなくなる。詩は意味を失ってしまった。
それにしても、こんなにも「からだ」とそれを指す語が用いられた文学作品がかつてあっただろうかと思うほどだ。彼女が身体性を見るのは人間にだけではない、父が眠る故郷シベリアのステップは〈母の髪の色と同じグレー〉だし、〈ステップというのは大地のむき出しのからだ〉だと言い切る。
私にとっていちばん大事なもののひとつは身体性、とりわけ、女性の身体性です。身体は家父長制との闘いの場。足のムダ毛を剃る、ワンピースを着る、化粧をする、ハイヒールを履くことを強いられます。身体をとおして女性への暴力が生じるんです、制度的にも現実的にも。女性の身体は常に観察の対象です。物事が始まる点なのです。まさに身体が、すべての女性を、すべての経験をひとつにしてくれる。誰だってフェミニズムへのまなざしを、書くことへのまなざしをもち得るんです、誰にだって自分だけの経験がある――でも身体と身体の体験が私たちをひとつにしてくれるんです。
インタビューでこう語るヴァシャキナは、『傷』の中で母のからだを詩にする。
死の二週間前に母は いつ起き上がれなく
なったか打ち明けた
彼女は気づいた おりものシートの分泌物が
変な匂いを発していることを私は彼女にきいた その匂いはなにに似てる?
彼女はこたえた その匂いは水に入ったことのない
古い船に似ていると
そのとき私はふざけて言った ママは詩人になっちゃったね
母は少し微笑んだ 詩人になったと言った理由を
彼女は理解していない そんな気がした
だけどそんなの簡単なこと――
ヴァギナの小舟が腐ってしまったのだから
女性たちは自分の経験を内部に凝縮させているが、それは文学には反映されてこなかった。多くの女性たちの生が表象されぬままだ、これがオクサーナの執筆の原点にある。
私は子どもの頃から不思議でした、なぜ大きな文学には自分の祖母がいないのか、なぜ詩にはうちのキッチンの戸棚が出てこないのか、私がマカロニを茹でるところ、私の祖母が癌で亡くなる場面がないのかと。人生の大部分は芸術の中に表象されていない、その人生のステイタスが低いからだということもあるのでしょう。だから私が全部書くことにしたのです。
癌になった母の体、乳房を失った母の体、〈まさに女性らしい女性〉だった美しい母から胸が消え、異臭を発しながら朽ちていくとき、オクサーナは〈母と私はひとつのからだ〉に生きていると言い、胸の膨らみに抵抗を覚えた自分と胸を失った母の身体を同一化していく。狭いベッドに毎晩一緒に寝ながら、触れ合う二つの体をとおして、母の死の痛みと自分の生の痛みをひとつにしていくのである。
旅の過程で母の骨壺を抱えながら「お母さんはもう私のもの」とつぶやく彼女は、最終章で母に直接語りかける――自分に言葉をくれたのは母だと。「私の舌=言葉は、あなたの舌=言葉から創られた」(ロシア語の「舌」という語は「言語」という意味ももつ)と。
さらにヴァシャキナは活動家でもある。2019年にモスクワで起きた「ハチャトリアン三姉妹事件」(奴隷状態にされ性的虐待も受けていた三姉妹が父親を殺害した事件)の際には、姉妹を擁護する意思表明をし、7月には仲間たちと彼女たちを支持するポエトリーリーディングを開催している。(4分24秒あたりから登場するのがヴァシャキナ)。
どうかお願いです、壁の向こうから、あるいは通りで女性の叫び声が聞こえたら、その暴力を可視化してください。「助けが必要ですか?」と訊いてください。「助けが要りますか?」「家まで送りましょうか?」「すぐに警察に電話しましょうか?」と声をかけてください。暴力をふるう者には、そいつのやっている忌々しい行為が間違っているんだということをその都度わからせないといけないんです。
母からもらった舌=言葉で、これまでの文学には不在だった女性たちの声を可視化していく、通りで見知らぬ女性を暴力から救うように一人ずつ。それがフェミニスト詩人・作家ヴァシャキナの仕事だ、それを痛感させられる一冊だった。

オクサーナ・ヴァシャキナの詩集
高柳聡子(たかやなぎ・さとこ)
早稲田大学大学院文学研究科ロシア文学専攻博士課程修了。文学博士。専門はロシアの現代文学や女性文学、フェミニズム・ジェンダー史。早稲田大学などでロシア語、ロシア文学を教える。著書に、『ロシアの女性誌時代を映す女たち』(群像社)。
「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」







