記事を検索する
「あの本がつなぐフェミニズム」第9回:『誰のために子どもを産むか』(大橋由香子)
2025/7/15

パソコンもネットもスマホもないころ、女たちは刺激的な考えや情報を雑誌や本から得ていた。今あらためて「あの本」のページを開くと、何があらわれるのだろうか。連載第9回は、人口政策のまやかしを教えてくれた理論書や、人口問題について対話した本です。少子化対策という名目で「産む/産まない」が当事者を置き去りにして、選挙活動の煽動の道具になっているいま、これまで語られてきたことをきちんと振り返りたいですね。
(バナー写真:フィリピンの女性たちとの屋外学習@マニラ1987年。背景写真は1982年優生保護法改悪阻止集会@渋谷山手教会、左の旗は1984年女と健康国際会議@オランダ/すべて提供:大橋由香子)
人口は、食糧の増加より速いスピードで増えていく。人口が増えすぎることによって、飢える人が増えてしまう。したがって貧困にあえぐ国の人口を減らせば、食糧がゆきわたる……かなり大雑把だが、マルサス主義や新マルサス主義というネーミングとともに、1970年代にとびかっていた言説だ。
アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど「第3世界」「低開発国」「開発途上国」と呼ばれる国への搾取や富の分配の不公平には目をつむり、人口を減らすべきという「先進国」の主張。そうした人口政策が日本国内と地続きだと、私の目からウロコが落ちたのは1984年オランダでの「女と健康国際会議」だと思っていた。(このウェブ連載のタイトル写真)。
でも、それより前の学生のとき、おそらく村井吉敬ゼミか鶴見和子ゼミで読んだ本が、人口政策のまやかしを私に教えてくれていた。
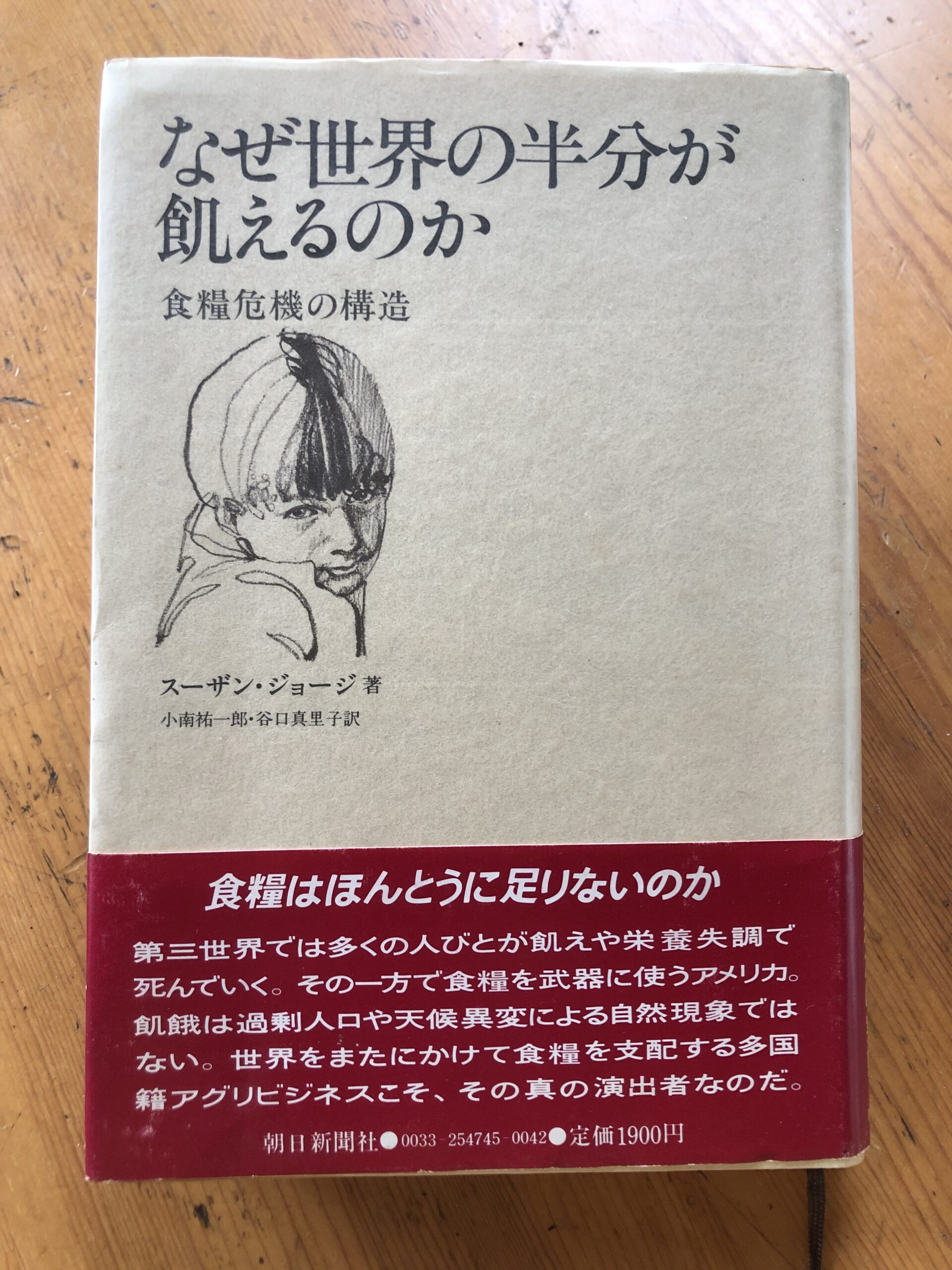
それが『なぜ世界の半分が飢えるのか 食糧危機の構造』である。日本語訳は1980年刊、小南祐一郎・谷口真里子訳、朝日新聞社(その後、朝日選書)。著者のスーザン・ジョージはアグリビジネス(農業関連産業)を研究し、1974年ローマで開かれた世界食糧会議に対する批判報告の執筆陣のひとり。「はじめに」で、こう書いている。〔 〕内は引用者の補足。
「〔ヨーロッパやアメリカの〕善意の人びとのほとんどは、マスメディアのおかげで、食糧危機というものを”宇宙船・地球号”の上にたまたま生じた自然現象の結果、あるいは本来解決などとうてい及びもつかないしろもの、ないしは後進国がむやみに子どもを増やした天罰、貧乏人自身の意欲の欠如と怠惰の問題だとみているのである。そこで私は改めて、公式に使われている決まり文句や広く行きわたっている神話を深く追求してみようと思う。」
人口が多すぎるから飢えるという「人口神話」。貧困や飢餓の原因は、過剰人口や天候異変ではないと著者は断言する。「緑の革命」や食糧援助、世界銀行の役割を分析し、世界の食糧を手中に収め、それを操りながら故意に食糧不足を作り出しているのは多国籍農業会社なのだ。そして、人口政策について、ジェンダーに注目した記述がある。
「低開発国では、実際に子どもを産む人びと、つまり女性に対して、ほとんど注意がはらわれていないのは驚くばかりである。私は冗談をいっているのではない。政府は外に向かっては出生率を減少させたいと表明しているにもかかわらず、女性(とくに農村部の女性)の教育をほとんどせずに、男子を優先させている。どの文化においても、女性の”教育”は結婚ーー時には一五歳前にすることもあるーーのための準備に限られていた。(中略)
人口を増加させる非常に大きな要因のひとつは、(略)”息子びいき”にある。女の赤ん坊はもはや山の上に捨てられはしないが、(略)女子の出生は、多くの地域で、未だに家庭の災難と考えられている。(略)〔このような状態では〕世の中の動きから隔絶された女性が、ほんとうは自分の身体は自分でコントロールできるのだということを知るようになるのか、全く見当がつかない」
女の子は教育を受けられず、男児が優遇され期待される社会。この本を読んだ当時の私は、テレビドラマ「おしん」時代の日本と重ねながら、遠い外国(低開発国)を思い浮かべていた。だが、再読してみると、現代の日本もあまり違わないように思えてきた。(将来のケアのためなのか、女の赤ちゃんのほうが歓迎されるよう変化したと言われるが、)女性が人口を減らしたり増やしたりするための道具扱いされる点は、50年前の「後進国」も、今の日本も、似たようなものではないだろうか。
避妊用ピルをプエルトリコの女性に使わせ安全性を確かめてからアメリカ合州国で使った話は有名だったが、スーザン・ジョージは本書で、ユーゴ(スラヴィア)の女性に新しい避妊薬を試していたこと(安全ではないとわかるとアメリカ本国の女性に使わない)、掻爬法と吸引法のどちらの中絶手術が女性の体に悪影響を及ぼすかの調査をしていたと指摘している。周縁化された女たちは、このように実験台にされている。(読んだ当時の私は、「吸引法」の意味がわかってなかったと思う。)
***
日本の人口政策を、ちょっとおさらいしてみよう。
80年前、戦争に負けた日本は、増えすぎた人口を減らす必要に迫られて、「少なく産んで、賢く育てる」と180度の転換をする。植民地化・占領したアジア太平洋諸国から、たくさんの人間が引き揚げてきた。空襲で焼け野原になり、住む家も食べるものもない。そこで、1948年の優生保護法によって、強制的な不妊化(優生=不妊手術)で「不良な子孫」が増えないようにし、同時に、刑法堕胎罪は残したまま中絶を例外的に医師に許可した。こうして、敗戦後の日本は、避妊ではなく人工妊娠中絶によって人口を減らすことに成功した。夫は長時間労働でお金を稼ぎ、妻は専業主婦として家事・育児・老人介護などアンペイド・ワークを担うという性別役割分業が、高度経済成長を支えた。
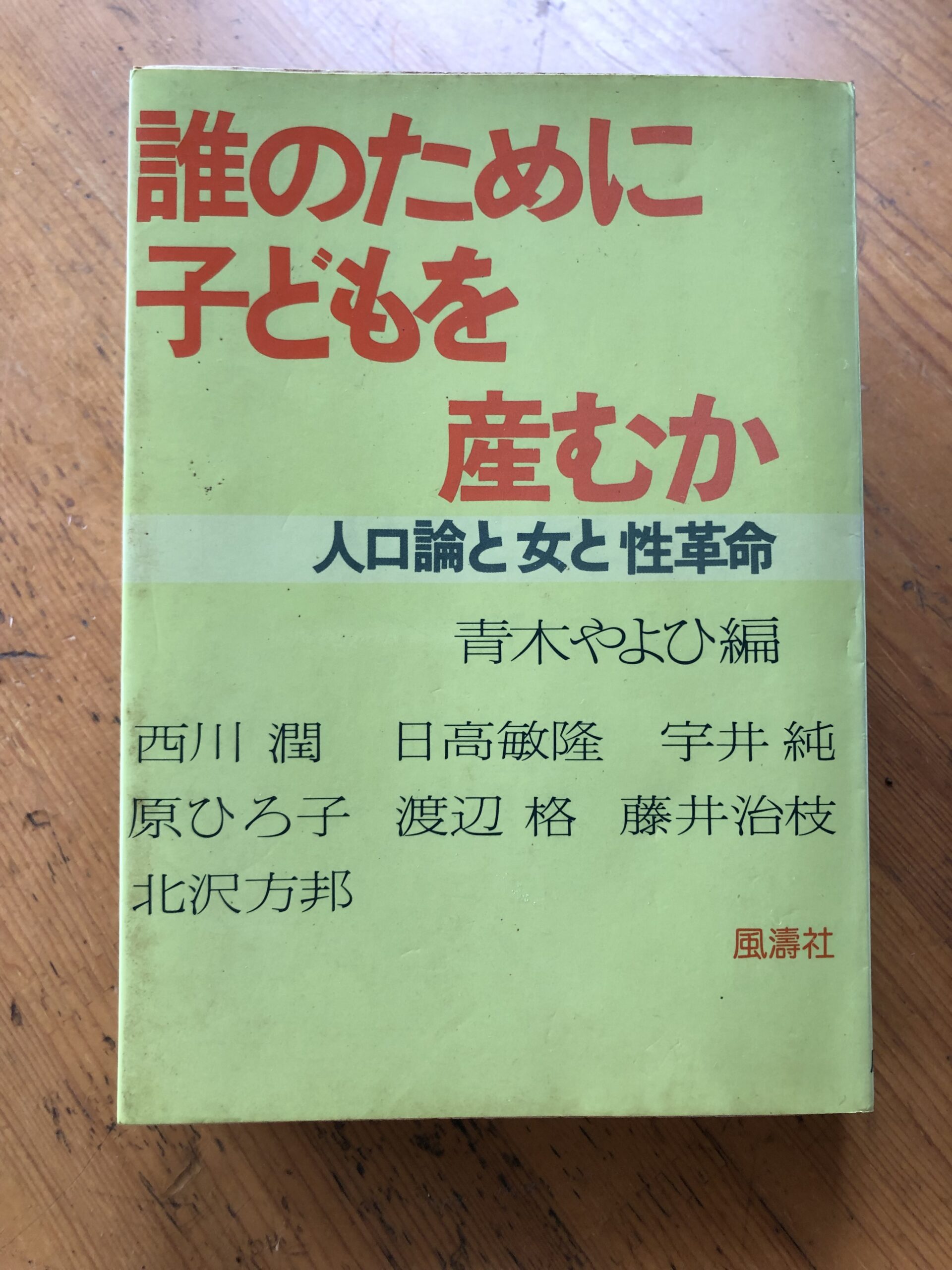
『なぜ世界の半分が飢えるのか』の原書が出た1976年に、青木やよひ編『誰のために子どもを産むか 人口論と女と性革命』が風涛社から刊行されている。
青木やよひは、こう書いている。
「私は終戦の時、一八歳だったわけですけれども、戦争中は産めよ増やせよということで、私たちの母の世代までは、子産み子育てで一生を終えるような人生を送っていた。そして戦争が終わったら、戦争したのも人口過剰のせいであったみたいなことが言われ、戦争責任もそこでうまく合理化されて、だからもう子どもは産んではいけないんだと全然変わってしまった。青春時代に価値の大転換を見てしまったわけで、非常に不信感を持ったということがあるんです」
そんな青木が、「産むことが、男性には持ちえない女性の誇るべき特質となるためには、一方で産まない自由が保証されていなければならない。『女は子どもを産むものだ』と『女は子どもが産めるのだ』というこの二つのことばのニュアンスのちがいを、一度考えてみたい」という思いから5人での座談会、3人との対談を収録したのが本書である。
「私たちにとって人口問題とは何か」と題した座談会では、国際経済学の西川潤、東大自主講座「公害言論」の宇井純、昆虫生理学の日高敏隆、文化人類学の原ひろ子と青木やよひが、環境問題、新しい価値観や多様性と人口について幅広く論じている。
日高氏が、母親の身体に悪い影響が残ることばかりが堕胎の社会的な問題とされるが、「母親にしてみれば、自分のお腹の中にいた子どもを殺すわけですね。(略)その辺はどうなんでしょう」と発言したのに対して、原氏は日本の間引きやヘヤー・インディアンの子捨てなどの例を紹介したり、現在でも中絶の後に一晩泣いている人もいれば、次の赤ちゃんが生まれればケロッとしている人もいたりと多様であることを説明している。(ちなみに、中絶について「子どもを殺す」と表現することへの違和感・問題点は2025年の今も常に感じさせられる)
また、分子生物学の渡辺格と青木やよひの対談「人間の生命と科学」では、胎児診断について、長いやりとりがあったあと
渡辺 長期的には確かに、胎児診断で、日本でも多くの家族は救われていると思います。中絶すれば、その子を産まなくて済むのですから。ただ、それは安易なのではなかろうかという気がします。
と発言している。渡辺氏は、もっと社会が(身障者に対して)万全の努力を払うべきだとも言っていて、先の日高氏も単純に中絶を否定しているわけではない。引用した言葉だけでは誤解を招くとも思うので全体を読んでほしいが、それでも、新しい価値観、よりよい社会を志向するラディカルな男性論者たちの避妊や中絶をめぐる認識と、青木やよひ、原ひろ子両氏との間には、微妙なズレや溝がある。全体は興味「深い」ものの「不快」にも感じる箇所があるのは、私の懐が浅さと50年という歳月のせいだろう。同時に、異なる見方をすり合わせて相手に伝えよう、対話しようとする「前向きさ」に感心する。
「私だって、(略)家へ帰れば、亭主関白ですからね。それに対して、ある言い訳をちゃんと作ってあるのです。というのは、人間は遺伝的に決定されていることは確かですが、もう一つは幼児環境で機械のある部分が作り上げられてしまう。だから私は、幼児環境で、女性蔑視という機械に作られてしまっているわけなので、今さらそれを変えることはできない。(略)女性蔑視の機械につくられ、家ではそれで動いている人間も、観念的には男女平等だと本当に考えているというところに、矛盾した人間の価値を認めて欲しいと、むずかしい問題を言っているわけです」
こう発言する渡辺格氏は、本書で一番年長の1919年生まれ。藤井治枝さん以外は、みなさん鬼籍に入られた。
この本に、紀伊國屋書店新宿本店のレシートがはさまっていた。日付は1982年7月末。国会で、優生保護法の中絶許可条件から「経済的理由」を削除する法改正を厚生大臣が約束し、中絶を禁止しようとする国会の動きに対して反対運動が盛んになっていく時期だ。この本を買って「理論武装」しようとしたのかな。四谷公会堂の会議の後に食事した随園、ゴールデン街のあの店この店、西口の「鬼の栖(いえ)」、模索舎、四谷の女性合同事務所ジョキを行き来する自分を、ドローンから見ている気分になる。(ジョキを含め、この頃のことは『わたしたちの中絶』石原燃・大橋由香子編著、明石書店の第Ⅰ部拙文を参照ください)
その後の日本では、結婚する人も出産する人もさらに減少するなか、出生率を上げるために、女性に注目が集まっていく。
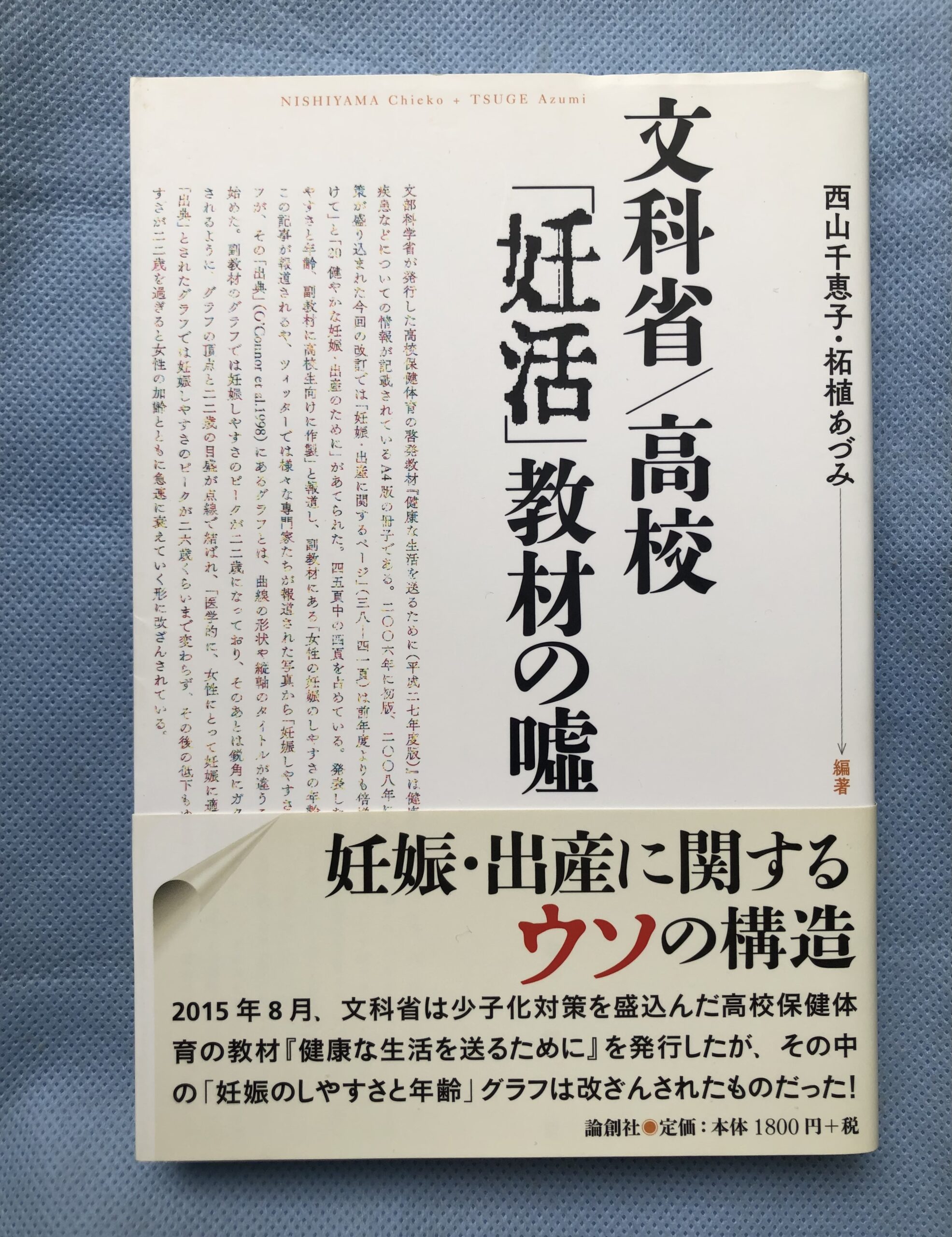
早く結婚して妊娠するよう啓発するために、卵子の老化を事実以上に強調したウソの「妊娠のしやすさと年齢」グラフが、2015年高校保健体育の副教材に掲載された。この経緯については、西山千恵子・柘植あづみ編著『文科省/高校「妊活」教材の嘘』(論創社、2017)をお読みいただきたい。私も「人口政策の連続と非連続—リプロダクティブ・ヘルス/ライツの不在」と題して、戦前の産めよ殖やせよ政策との共通点について書いている。
しかし残念なことに、政府と地方自治体は、多様なライフスタイルやセクシュアリティを否定するかのように、婚活や妊活を生徒たちに勧め続けている。最近では、プレコンセプションケアという謎の事業も推進している。
「誰のために子どもを産むか」という50年前の本の問いかけに対して、「将来の年金のため」「日本民族を滅ぼさないため」「地方の過疎化を救うため」などという声が、どんどん大きくなっていく。
振り返ってみると、「自分の身体は自分でコントロールできる」「私の体のことは私が決める」「My Body My Choice」という大切で当たり前なことが、「出生率上昇・少子化対策」というお化けによって阻まれてきたことがわかる。
「産んだほうがいいよ」「産まないと大変だよ」という脅しや圧力からどうやって逃れるか。出生率の低下は、消極的なストライキ、あるいはサボタージュであり、生き延びるための選択なのかもしれない。卵子を冷凍しておくことも、「産みなさい」「母になりなさい」プレッシャーをかわすため、「産む準備してますよ」というポーズの場合もあるかもしれない。
そんな圧にとらわれずに、自分の体の主人公になれる社会を! と叫びたい。
*新しい本が2冊でました。
『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』
AERA「この人のこの本」に著者インタビューが掲載されました。

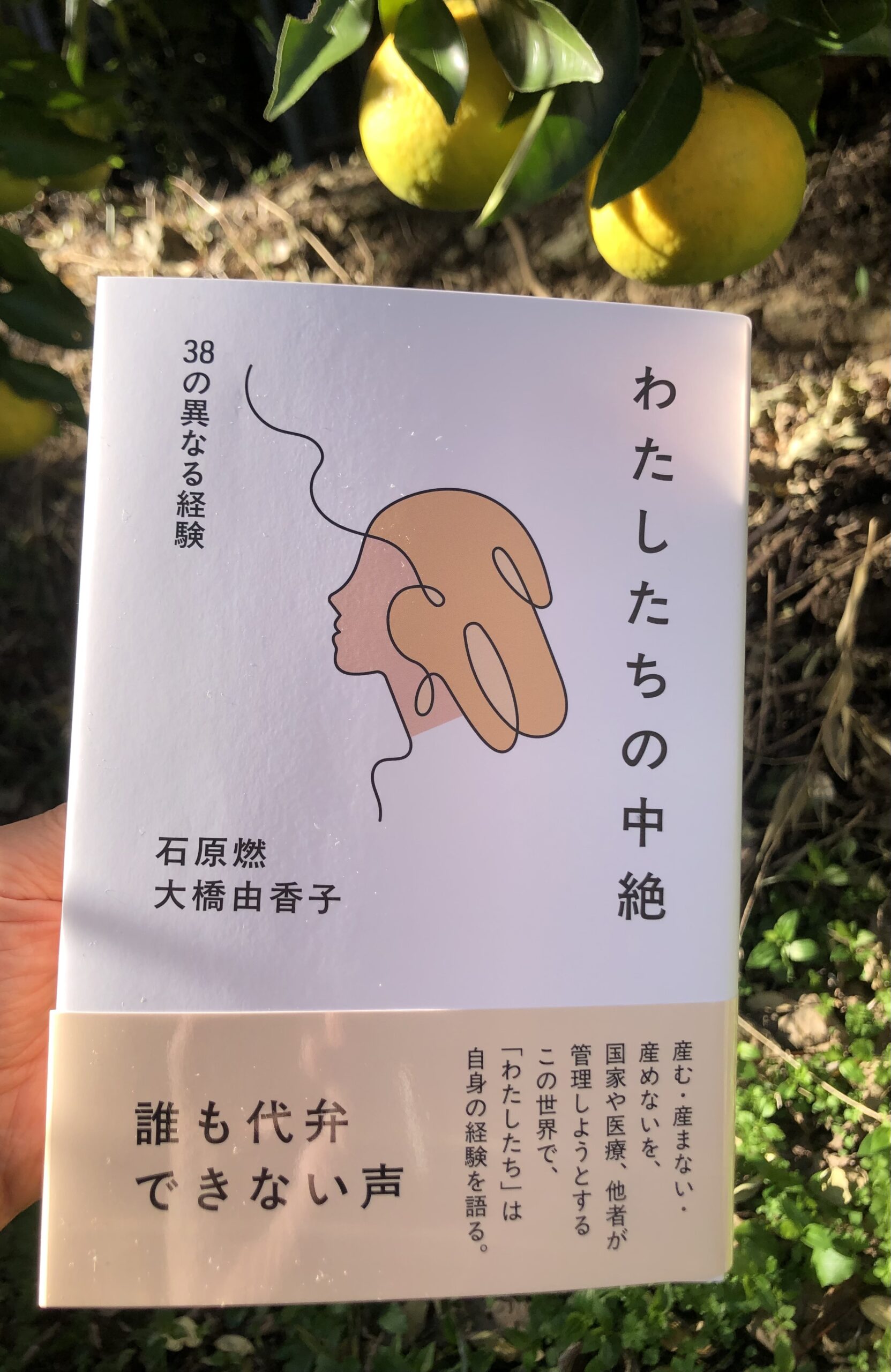
大橋由香子(おおはし・ゆかこ)
フリーライター・編集者、非常勤講師。著書に『満心愛の人―フィリピン引き揚げ孤児と育ての親』(インパクト出版会)、『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』(エトセトラブックス)、共編著『福島原発事故と女たち』(梨の木舎)、『わたしたちの中絶』(明石書店)ほか。光文社古典新訳文庫サイトで「字幕マジックの女たち:映像×多言語×翻訳」連載中。白水社のPR誌「白水社の本棚」2025夏号に「小尾芙佐さんのこと」を寄稿。小尾さんについてより詳しいことは、『翻訳する女たち』をぜひお読みください。
大橋由香子「あの本がつなぐフェミニズム」
- feminista
- nomore女人禁制
- uhi
- あの本がつなぐフェミニズム
- ある在日朝鮮人のフェミニストが考えていること
- ヴァージニア・ウルフ
- エトセトラ
- エトセトラ VOL.6
- カルメン・マリア・マチャド
- カン・ファギル
- すんみ
- フェミニスト出版社
- フェミ登山部
- みんなでパブコメ
- よこのなな
- ラテンアメリカ
- 伊藤春奈(花束書房)
- 堀越英美
- 大橋由香子
- 女人禁制
- 小山さんノート
- 小山内園子
- 小林美香
- 小澤身和子
- 山内マリコ
- 山姥
- 山田亜紀子
- 岩間香純
- 新水社
- 松田青子
- 枇谷玲子
- 柚木麻子
- 牧野雅子
- 王谷晶
- 田嶋陽子
- 田房永子
- 石川優実
- 福岡南央子
- 緊急避妊薬を薬局で
- 翻訳する女たち
- 翻訳者たちのフェミニスト日記
- 部落フェミニズム
- 鈴木みのり
- 長田杏奈
- 高柳聡子







