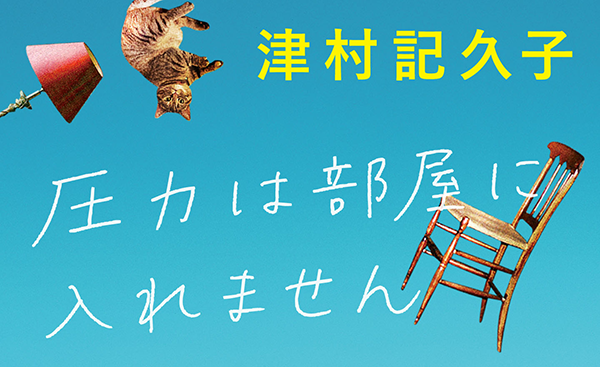記事を検索する
フェミ登山部「あの日、山で見た景色」第20回:労働運動としての山登り(ぱく)
2025/3/15

「フェミ登山部」とは、主に関西近郊の山を巡ったり、ときどき遠くの山に登ったりもする、トランスやクィア、シスとヘテロも参加する多様なフェミニストたちのコレクティブ。メンバーたちが山を登りながら、ときに下りたあと考えたあれこれを、リレー形式で連載します。第20回は、ぱくさんが山に戻ってきた現在から、これまでの来し方と労働運動を振りかえってくれました。「変えるために声をあげなければいけない。だけど、今は元気がない。だから山に登ろう」!
15年ほど前、仕事仲間とよく山に登っていたことを思い出す。その頃の私は最長3年という年限付きの非正規雇用で、私立大学で授業運営のサポートや学生の作文の添削をする仕事をしていた。
学生生活を終えてはじめて就いた仕事だったこともあり、最初のうちは有期雇用のグロテスクさをあまり実感できていなかった。たしかに契約書には「1年契約、更新2回まで」と書いてはある。だけど担当業務がなくなるわけでもないのに3年経ったら自動的にクビになるだなんて、そんな不条理がまかり通るはずがない。どうせ形骸化した規定だろうと、どこか楽観的に構えていた。
まかり通るはずのない不条理がまかり通ってしまうことを目の当たりにするのは、働き出してはじめての年度末。更新上限を迎えた多くの教職員がひっそりと職場を追われ、翌4月から同じポジションに新しい人があてがわれる。3年かけて培った経験や信頼関係はリセットされるのに、頭数だけ揃えれば問題ないだろうと、人を部品のように扱ってしまえる制度が恐ろしく、それを仕方のないことだと諦め受け入れてしまう現場の空気がもどかしかった。こうした首のすげ替えは、自分の職場だけでなく、全国の多く大学や公共機関でも起こっているのだと知り、問題の根深さに驚愕する。
働く人を使い捨てにする制度をこれ以上許してはいけない。そう思って同僚たちと小さな労働組合を結成し、大学と交渉を始めた。自分たちの主張に迷いはなかったけど、はじめての組合活動は想像以上にエネルギーを消耗した。団体交渉で交わした約束ごとを簡単に反故にする大学当局への怒りもさることながら、最も深く絶望したのは、雇い止めによって生じる現場や学生にとってのデメリットを承知しながらも、決して波風を立てようとしない上司(彼らもまた非正規雇用である)、理解しているよと目配せしながら、表立っての支援は拒む専任教員、そして、性差別と切り離せないはずの非正規雇用の問題にひたすら無頓着なフェミニストの「先生」など、それまで信頼や尊敬の念を寄せていた人たちの態度だった。
そんな中で、癒しを求めるようにはじめたのが山登りだ。一緒に登る仕事仲間は、同じ非正規雇用の立場で、しかし組合活動とは距離を置いている人たちだった。組合員ではないからと言って、自分たちの労働環境に納得しているわけではない。私たちは山道を歩きながら、自分たちの仕事が軽んじられていることの虚しさや、意見を聞いてもらえないことの悔しさ、雇い止めによって引き裂かれることの不安など、日頃のモヤモヤを語り合った。
署名を集めたりビラを撒いたりデモをしたりストライキするような形ではなくとも、この山登りの会もある種の労働運動だったのではと、振り返って思う。同じ立場で働く人同士が自分たちの仕事の価値を肯定し、お互いをケアし合う行為は、団結するための第一歩だ。グチをこぼすだけでは何も変わらないという意見もあるが、少なくとも私はこの山登りの会がなければ、燃え尽きずに組合活動を続けることはできなかっただろう。
大文字山からはじまり、鷲峰山、比叡山、愛宕山、皆子山、伊吹山、大山と少しずつ標高をあげながら1年間でたくさんの山を登ったが、2年目を迎えることはなかった。メンバーのほとんどが雇い止めになり、仕事も住む場所もバラバラになったからだ。私自身も雇い止め撤回争議と新たな食い扶持探しに精一杯で、山登りを呼びかける時間と心の余裕はなく、気づけば山も、労働運動さえも遠い存在になっていった。
それから15年。この間にもいくどかの雇い止めを経験したのちようやく無期雇用となり、契約満了の心配から解放されたタイミングで、フェミ登山部を知る。自分の中に閉じ込めていた山への想いがむくむくと湧き上がってくるのを感じ、友人を通じて入部(?)させてもらった。
参加してみて驚いたのは、アカデミア以外にこんなにもフェミニストがいるんだということ。働いている人も働いていない人も、年齢もセクシュアリティもさまざまな人たちが、みんなそれぞれの場所で活動しながら、月に一度山に集まるゆるやかなネットワークは、今のところとても刺激的で居心地がいい。かつて有期雇用の反対集会などを共に主催した仲間たちとの嬉しい再会もあった。私が賃労働に明け暮れ、山からも運動からも遠のいていた間にも、こうして社会と関わり、アクションを起こしてきた人たちがいるんだと思うと、感慨深くも、己が恥ずかしくもある。
とはいえ15年たった今でも非正規を取り巻く環境は一向に改善していない。この3月31日にもまた、多くの労働者が何の理由もなく、職場を追われることになるだろう。
この状況に慣れてはいけない。変えるために声をあげなければいけない。だけど、今は元気がない。だから山に登ろう。山に登って少しずつ、また闘うための英気を養うのだ。
 2010年夏。伊吹山山頂にて日の出を望む
2010年夏。伊吹山山頂にて日の出を望む
 2024年秋。はじめてのフェミ登山部参加。市ケ原に向かう途中の見晴らし展望台にて
2024年秋。はじめてのフェミ登山部参加。市ケ原に向かう途中の見晴らし展望台にて
ぱく
80文字のプロフィールを埋めるのも四苦八苦する程度に、自己紹介が苦手なシス・ヘテロ。ジェンダー、セクシュアリティとエスニシティ、そして労働問題が主な関心事。
フェミ登山部(ふぇみとざんぶ)
2022年春から活動を始めた、月1ペースで主に関西近郊の山を巡る(時々遠出もする)、トランスやクィア、シスとヘテロも参加する多様なフェミニストたちのコレクティブ。トランス差別をはじめとしたあらゆる差別に反対し、自身の特権性に向き合いながら学ぶ姿勢を持つ20代から70代までの幅広い年齢、そして様々な経験を持つフェミニストたちが参加している。
「あの日、山で見た景色」フェミ登山部
- feminista
- nomore女人禁制
- あの本がつなぐフェミニズム
- ヴァージニア・ウルフ
- エトセトラ
- エトセトラ VOL.6
- カルメン・マリア・マチャド
- カン・ファギル
- すんみ
- フェミニスト出版社
- フェミ登山部
- みんなでパブコメ
- よこのなな
- ラテンアメリカ
- 伊藤春奈(花束書房)
- 堀越英美
- 大橋由香子
- 女人禁制
- 小山さんノート
- 小山内園子
- 小林美香
- 小澤身和子
- 山内マリコ
- 山姥
- 山田亜紀子
- 岩間香純
- 新水社
- 松田青子
- 枇谷玲子
- 柚木麻子
- 牧野雅子
- 王谷晶
- 田嶋陽子
- 田房永子
- 石川優実
- 福岡南央子
- 緊急避妊薬を薬局で
- 翻訳する女たち
- 翻訳者たちのフェミニスト日記
- 部落フェミニズム
- 鈴木みのり
- 長田杏奈
- 高柳聡子